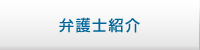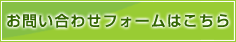弁護士古賀克重は20年以上、患者側弁護士として医療過誤訴訟、薬害エイズ訴訟、ハンセン病訴訟、薬害C型肝炎訴訟などにかかわってきました。
その経験からテレビ・ラジオ・新聞・雑誌からの取材や出演を受けることが多く、様々な医療問題について情報発信してきました。このページではそのようなメディア出演の際に情報発信してきた医療情報の中から抜粋して説明しています。
ラジオ
-
Q 薬害C型肝炎の救済はいつまで、どのようにすれば良いのですか?(ラジオLOVEFM「ラブスタ法律相談所」2017/11/14出演より)

A 平成15年に国と製薬企業を被告に裁判が始まり、5年の月日を経て、平成20年に救済法が成立しました。当初の請求期限は5年でしたが、その後請求期限が延長され、その延長された期限が来年1月15日に迫っているのです。
救済法に基づき、九州だけでも370名近くの原告が和解に至っていますが、今現在も裁判が続いています。
C型肝炎に感染した患者さんの中でも、フィブリノゲン製剤などの特定の血液製剤を使用されたことによって、C型肝炎に罹患してしまった方が対象になります。患者さんがすでに亡くなられている場合は、ご遺族が原告として請求することができます。
-
Q 無痛分娩とは何が問題ですか?(ラジオLOVEFM「ラブスタ法律相談所」2017/8/8出演より)

A 無痛分娩とは、出産の痛みを麻酔で和らげることを目的にした医療行為をいいます。
分娩時に痛みを感じたタイミングで硬膜外麻酔(こうまくがい・ますい)を行うものです。様々なニーズに応えるための差別化として積極的に取り組むクリニックもあります。
また高年齢出産などハイリスク出産に対する対応という面があります。つまり、妊婦自体が痛みを回避するために自ら希望する場合と、妊婦の身体的合併症のために医学的に選択される場合があるのです。この硬膜外麻酔で重大な事故が相次いで発覚しているんです。 -
Q 病院で予期せぬ後遺障害が残りました。自分のカルテを開示することはできますか?(ラジオLOVEFM「ラブスタ法律相談所」2017/5/9出演より)

A 後遺障害が残った、家族がいきなり命を落とした・・そのような医療事故が発生した場合、その医療事故が医療機関のミスによるものか、医療過誤といえるのか、損害について賠償してくれるのか。
その判断のためにはカルテを分析することが必要不可欠になり、そのためにはカルテ開示する必要があります。
厚生労働省も、診療情報の提供に関する指針を定めています。「医療従事者等は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければならない」とするほか、「医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならないと定めているのです。
-
Q 医療事故調査制度はどのような制度ですか。また運用状況は?(ラジオLOVEFM「ラブスタ法律相談所」2016/10/11出演より)

A 患者が予期せぬ死亡した場合、医療機関が必要な調査を行って事故原因を調べるという制度です。
医療事故の「原因究明」と同種事故の「再発防止」、この2点を目的にしています。
厚生労働省は年間1000件から2000件を想定していました。ところが、この1年間でわずか356件にとどまりました。予想の3分の1から5分の1という数字になります。
医療機関側が「予期せぬ死亡」という判断をしていないケース、遺族も制度自体を知らないケースが多いようです。医療機関への働きかけはもちろん、患者に対しても周知徹底していく必要があります。また医療機関や地域によって180度見解が違うこともあると言われていますから、報告対象となる医療事故に該当するか、その判断が統一化・標準化されるように工夫していく必要があるでしょう。
-
Q 医療事故にあった場合、病院に過失があるかどう調べれば良いですか?(ラジオLOVEFM「ラブスタ法律相談所」2015/12/22出演より)

A 法律上は結果責任でないため、病院が医療水準に照らして、なすべきことをしていない場合、つまり、過失によって悪い結果が出た場合にはじめて、損害賠償請求が可能になります。
医療過誤・医療事故を専門に取り扱っている弁護士は、カルテを読み込み、医療文献や医療論文、ガイドラインを調べるほか、第三者の医師からヒアリングするなどして、責任追及が可能か調査していきます。
この医療調査をまず行って、責任追及の可能性を調べるわけです。
最近では、出産の吸引分娩で、子どもさんに血腫が生じて死亡したケースがあります。 医療調査を行った結果、吸引分娩を継続したことについて、慎重に手術をすべき注意義務に違反したと考えられました。そこで病院と示談交渉をしたところ、病院が非を認めて示談成立しました。また胃癌手術で縫合不全を生じて亡くなってしまったケースもありました。胃癌手術などで縫合不全が生じて、胆汁が流れ出して、多臓器不全になったものです。手術後に患者さんが痛みを訴えて、ガーゼもかなり汚染されているのに放置していました。
術後管理が適切に行われていないと主張して、病院と示談が成立しました。 -
Q 老人介護施設での医療事故はどのような傾向ですか?(ラジオLOVEFM「ラブスタ法律相談所」2015/11/10出演より)

A 日本もかなり高齢化社会が進んでいますので、老人介護施設での医療事故が増えており、相談も増えています。
高齢者が施設内で転倒したり、食事中に窒息したり・・その他にもトイレでの転倒、風呂場での呼吸不全などです。介護施設や病院が、患者さんの健康状態に照らして、十分に観察していたか、必要な場合には転院措置をとったかが法的に問題になります。
私の経験した事案では、80代の高齢者が自宅階段から転倒して頭部を強打したケースがあります。
御家族が心配して病院に入院をお願いしたのですが病院が「大丈夫ですよ」と帰宅させてしまいました。
ところがその日の夜に急変して寝たきりになったんです。病院と交渉しまして、病院が経過観察義務違反を認めて無事示談が成立しました。 -
Q 美容医療ではどのようなことが問題になりますか?(ラジオLOVEFM「ラブスタ法律相談所」2015/9/8出演より)

A 美容医療は、医療行為の緊急性と必要性が他の医療分野と比較して少ない特徴があります。しかも患者さんが結果の実現を強く希望している特殊性もあります。
ですから医療機関は、治療効果の見通しはもちろん、治療によって生じる危険性についても、より十分に患者に説明すべき義務を負っています。トラブル防止のコツとしては、「美容医療を希望する患者さんは、十分に時間をかけて手術をするか決める」、「不安があれば何度でも遠慮なく質問する」そして「その質問に不愉快な対応を見せる医療機関であれば、そもそもトラブルが起こりやすいですから避けた方が賢明だ」ということです。
新聞・雑誌
-
Q 医療被害者が集団で国に解決を求めることもあるのですか?(「素顔の弁護士」朝日新聞 2015/1/8)

A 「あなたの愛する人は大丈夫ですか」
師走の天神で、20人近い学生が大声を出し、汗をかきながらビラを配った。肝炎に感染する危険性の高い血液製剤フィブリノゲン。80年以降、約29万人に投与され、1万人以上が肝炎に感染したと指摘される。既に74人の被害者が全国5地裁で国や企業を相手に裁判を起こしている。昨年12月、製剤の納入医療機関が公表されたのを受け、裁判を支える学生が福岡、東京、大阪、名古屋、仙台で肝炎検査を呼びかける一斉行動を行った。
日本の裁判というと、傍聴席には誰もおらず、専門家だけで物事を決めるイメージがつきまとう。分かりにくい、遅い、そして冷たい。だが、被害者が多い集団訴訟では、支援者の行動が誤解されがちな裁判に本来の血を通わせる。
九州大の講義に、原告の女性が呼ばれた時のことだ。女性は出産の際、止血剤としてフィブリノゲンを使われて感染した。講義で「『自分のせいで母親が肝炎に苦しんでいる』。そんな息子の気持ちがやるせない」と語った。
講義後、当時1年生だった学生が泣きながら駆け寄ってきた。「幼い頃、母が病気で入院して、子どもとして苦しんだので私も分かります」
被害者には、この原告と同じように出産時に感染したお母さんが多い。「自分の母親が被害者だったら。自分を産む時に感染したとしたら」。共感が学生の間に広がった。現在、九州大、西南大、福岡大、久留米大、第一薬科大の200人近い学生が支援の輪に加わる。法廷傍聴を続け、模擬裁判や学園祭での講演などを企画してくれる。
「私たちはあなたの苦しみを想像することしかできません。でも、あなたが未来を信じる限り、あなたの足元を照らす光にも、あなたの背中を押すやわらかな風にもなろうと思います。それが私たちにできる小さな応援です」
これは、ある学生が支援集会で原告に贈った詩の一部だ。裁判に無縁の生活を送ってきた原告にとって、社会的注目を集める裁判を闘い続けるプレッシャーは少なくない。「自分を応援してくれる人がいる」。そんな思いこそが原告の大きな支えになる。
支援者は学生だけではない。ボランティアや医療関係者、薬害スモン訴訟やHIV訴訟の元原告も毎回傍聴に駆けつけてくれる。
療養所に強制隔離された被害を争い、勝訴判決・控訴断念を勝ち取ったハンセン病訴訟の元原告に話してもらう機会があった。
「私たちは証言することで、そこから新たな人生を歩むことができました。裁判を通じて人生を取り戻したのです。皆さんは被害者です。何も悪いことをしたのではありません。堂々と被害を語ってください。おのずと道は開けてくるはずです、私たちのように」
そのエールは弁護団にも向けられているように感じた。もしかすると、支援者に一番支えられているのは、われわれ弁護士なのかもしれない。