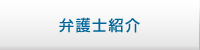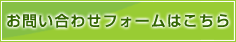麻酔薬投与における麻酔医の過失と因果関係についての最高裁判決
最高裁が、全身麻酔と局所麻酔の併用による手術中に生じた麻酔による心停止が原因で患者が死亡した場合において、麻酔医に各麻酔薬の投与量を調整すべき注意義務を怠った過失があり、同過失と死亡との間に相当因果関係があると判断しました。
医師の過失と死亡との因果関係が認められない場合も、最高裁は、過失がなければ患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性が認められれば、医師の不法行為責任を認めています(平成12年9月22日最高裁)。同じ理論で、重大な後遺障害が残らなかった相当程度の可能性が認められれば、やはり責任を認めています(平成15年11月11日最高裁)。
医療過誤分野では著名な最高裁判例ですが、「相当程度の可能性」の外延は不明確で、判断する裁判所によってかなりのぶれがあります。
患者側からみると、ダイレクトに過失と結果との因果関係を認めても良いではないかと思われるケースにおいても、裁判所が、安易に「相当程度の可能性」に逃げ込んでいるのではないかと思えることもあります。
この点、平成21年3月27日最高裁判決(判タ1294号70頁、判時2039号12頁)は、1審は原告の請求棄却、2審は相当程度の可能性限度の責任を認めたケースで、因果関係を認めて破棄差し戻しました。
この最高裁については、「死亡との因果関係ある過失の評価・検討を厳密に行うことなく、安易に救済法理である生存可能性侵害論に赴いてはいけないという含意を受け止めるべきである」(加藤新太郎・判タ1313号55頁)とも指摘されています。
事案は次の通りです。
左大腿骨を骨折した65歳の患者が、全身麻酔と局所麻酔を併用して人工骨頭置換術を受けたところ、術中に急激に血圧が低下して心停止して死亡しました。
この患者には、全身麻酔薬としてプロポフォールが、局所麻酔薬として塩酸メピバカインが使用されました。
プロポフォールは、能書によれば、以下のように指摘されていました。
一般に高齢者では、肝、腎機能及び圧受容体反射機能が低下していることが多く、循環器系等への副作用があらわれやすいので、投与速度を減速する (例えば、導入時の投与速度を約1/2すなわち本剤約0.025mL/kg/10秒に減速する) など患者の全身状態を観察しながら慎重に投与すること。
また、塩酸メピバカインは、能書によれば、やはり以下のように指摘されていました。
一般に高齢者では、麻酔範囲が広がりやすく、生理機能の低下により麻酔に対する忍容性が低下しているので、投与量の減量を考慮するとともに、患者の全身状態の観察を十分に行うなど慎重に投与すること。
最高裁は、注意義務について、
「プロポフォールと塩酸メピバカインを併用する場合には、プロポフォールの投与速度を通常よりも緩やかなものとし、塩酸メピバカインの投与量を通常よりも少なくするなどの投与量の調節をしなければ、65歳という年齢の患者にとっては、作用が強すぎて、血圧低下、心停止、死亡という機序をたどる可能性が十分にあることを予見し得たものというべきであり、そのような機序をたどらないように投与量の調整をすべき義務があったというべきである」
と判断したものです。
これに対して原審は、上記注意義務は認めつつ、「医師の裁量論」を過失の「回避可能性」の中に持ち込むという分かりにくい論法で、死亡に対する責任を認めませんでした。
つまり、「仮に投与量を減らしたとしても、その程度は麻酔医の裁量に属するものであり、その減量により死亡の結果を回避することができたといえる資料もない。・・従って死亡を回避するに足る具体的な注意義務の内容(死亡と因果関係を有する過失の具体的内容)を確定することは困難である。そうするとと、過失があったとはいえない」 と判断していました。
しかしながら最高裁はこの論旨を明確に排斥しており、結果回避可能性について、いわゆる抗弁説にたったという見方もできるでしょうし、結果回避可能性について言及しながらも、要は、因果関係の判断において、立証責任を医療機関側に課した(窪田充見・私法判例リマークス2010(上)57頁)ともいえます。
いずれにしろ患者側弁護士としては、裁判所に対して、因果関係の存否が微妙な事案で安易に相当程度の可能性に逃げ込まないよう注意喚起するために、最終準備書面等で引用できる最高裁ですし、また、2つの麻酔薬の能書の内容から規範的な注意義務を設定した手法自体も、参考になる事例判決といえるでしょう。