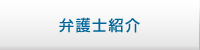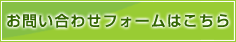急性脳症の小学6年生の患者を適時に適切な医療機関へ転送すべき義務を怠ったため、身体障害者等級1級に該当する後遺症が残存したケースについて、転送が行われていたならば患者に重大な後遺障害が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されるときは、医師に損害賠償義務があるとした最高裁判決
最高裁平成15年11月11日判決は、急性脳症の小学6年生の患者を適時に適切な医療機関へ転送しなかったため、身体障害者等級1級に該当する後遺症が残存した場合において、開業医に患者を高度な医療を施すことのできる適切な医療機関へ転送義務があると判断した上、転送が行われていたならば患者に重大な後遺障害が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されるときは、医師に損害賠償義務があるとして、患者敗訴の原審を破棄差し戻しました。
事案
当時、小学校の6年生だった患者は、昭和63年9月27日ころから発熱し、29日午前、1人で本件医院に行って診察を受けました。医師は、上気道炎、右けい部リンパせん炎と診断し、抗生物質や解熱剤アセトアミノフェンを処方しました。
改善しなかった患者は、同月30日(金曜日)午後7時ころ、本件医院の診察を受けました。医師はへんとうせん炎を病名に加え、2倍量の処方をし、10月3日(月曜日)に来院するよう指示しました。
10月2日(日曜日)、患者は朝から食欲がなく、昼から再び発熱し、むかつきがあったため、患者は同日午後2時ころ、本件医院が休診であったため、母親が付きって、B病院で救急の診察を受け、鎮痛剤を処方されました。
患者は、同日午後11時30分ころ、大量のおう吐をし、その後も吐き気が治まらなかったため、翌3日午前4時30分ころ、母親に付き添われ、B病院で救急の診察を受けた。B病院の医師は、腸炎と診断し、また、虫垂炎の疑いもあるとして本件医院での受診を指示しました。
そのため患者は、同日午前8時30分ころ、母親に付き添われ、本件医院で診察を受けました。
医師は約4時間にわたり、患者に700ccの点滴による輸液を行いましたが、点滴開始後もおう吐し、症状は改善しませんでした。
ところが医師は、おう吐が続くようであれば午後も来診するように指示をして、患者を帰宅させてしまいます。
患者は、帰宅後もおう吐が続いたため、同日午後4時ころ、母親に付き添われて本件医院の診察を受け、再び4時間にわたり、700ccの点滴による輸液を受けましたが、点滴中もおう吐が治まらず、さらに軽度の意識障害を思われる言動がありました。
そのため、患者の言動に不安を覚え、看護婦を通じて医師の診察を求めましたが、外来患者の診察中であった医師は、すぐには診察しませんでした
点滴終了した同日午後8時30分ころ、点滴終了後に診察を受けましたが、いすに座ることができないような状態でした。
翌10月3日早朝からは母親が呼びかけをしても返答しなくなり、同日午後9時前ころ、受診しましたが、意識の混濁した状態であり、呼びかけても反応がなかったため、医師は緊急入院が必要と考え、紹介状を交付して総合病院に入院させるに至りました。
しかい患者はその後も意識が回復せず、その後も急性脳症による脳原性運動機能障害が残り、身体障害者等級1級と認定され、日常生活全般にわたり常時介護を要する状態になるとともに、精神発育年齢が2歳前後で言語能力もないなどとして、後見開始の審判を受け、成年後見人が付されたというケースです。
争点
まず開業医の転送義務違反の有無が争われました。これについて最高裁は、開業医の転送義務違反を認めました。既に最高裁は(平成9年2月25日判決)、「開業医の役割は、風邪などの比較的軽度の病気の治療に当たるとともに、患者に重大な病気の可能性がある場合には高度な医療を施すことのできる診療期間に転医させることにある」と判断しており、本最高裁判決は具体的あてはめを行ったものです。
次に適時・適切に転送されていても、患者に重大な後遺障害が残らなかったという高度の蓋然性が立証できない場合でも、患者に重大な後遺障害残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されるときは、医師は上記可能性を侵害されたことによって被った損害を賠償すべき不法行為責任を負うと判断しました。
ポイント
一審・原審は、患者が自分でトイレに行ったり、診察時に嘔吐がいったん治まっていたことを重視して、転送義務違反を否定していました。
これに対して、最高裁は、これらの事実に言及することなく、転送義務違反を認めています。つまり最高裁は、患者の一時的な症状を過度に重視することなく、一連の症状が指し示すものを適切に把握することが大事であることを示唆しています(判例タイムズ1184号「平成16年度主要民事判例解説」74頁)。この点、差戻後の控訴審も、「意識障害は、その進行の過程で、一進一退の動揺性の現れ方をすることがり、意識障害を来す疾患は重篤で危険なものが多く、意識障害のレベルが動揺する場合に、覚醒状態に近い状態があることをもって意識障害ないと判断することは非常に危険であることから、その初期の意識障害見いだし、早期診断、早期治療に結びつけるのが臨床医の責務であるといわれている」と説示しています。
また「相当程度の可能性」については、患者が死亡したケースについて可能性侵害の法理を判断した最高裁平成12年9月22日判決の法理を、重度の後遺障害の場合にも適用したものといえます。
では重度ではない後遺症一般にも適用されるかは見解が分かれるところです。「判旨の文章中、特に重大な後遺症が患者に残った場合には、との限定的なニュアンスは存在しないので、後遺症が残存した場合は、全てにこの法理が適用されると解すべきであろう」(民事法情報218・102)とい見解も有力であり、実際、下級審判決は判断を広げる傾向にあります。中には医療過誤以外の分野の裁判例も散見されています。