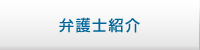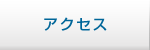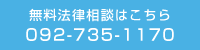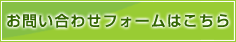介護老人施設に入所中の70代女性が居室内トイレで転倒し約1カ月後に死亡した事案で、施設職員が初回ナースコールから約20分駆け付けなかった等から転倒防止義務違反を認定した高松高等裁判所令和6年10月24日判決
事案
左半身麻痺等から社会福祉法人が運営する介護老人保健施設に入所する70代女性の亡Aは、1月13日午後6時30分頃、排せつの介助を求めてナースコールをした後に居室内のトイレで車椅子から転倒し、頭部外傷等の傷害を負い、急性硬膜下血腫により約1カ月後に死亡したことから、相続人らが、施設には転倒防止義務違反及び救急搬送義務違反があったとして、計約4400万円を求めて訴えを提起しました。
一審の高松地裁丸亀支部は、施設職員が初回のナースコールから約20分までの間にAのもとに駆け付けなかった等から、Aの転倒を防止すべき義務を怠ったとして、施設の転倒防止義務違反を認定して、遺族3名に対して合計約2700万円の支払いを命じました。
また、死亡逸失利益につき、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の年額合計78万3379円を基礎収入とした上で、「年金の性質やその年額等を踏まえると、上記年金収入の70%を生活費として控除するのが相当である」とし、「Aは75歳の女性であり、その平均余命の16年間を喪失期間として認めるのが相当である」と判断しました。
双方控訴の二審の高松高等裁判所は、一審判決を維持し、双方の控訴を棄却しました(確定。自保ジャーナル2185号153頁)。
争点に対する裁判所の判断
一審裁判所は、本件事故発生時において、Aは、トイレ使用に際して、立位の保持や移乗動作あるいは衣服の上げ下げについて、介助なしにこれを適切に行い得るだけの十分な身体能力を有しておらず、これを単独で行わせた場合には、転倒事故を生じる危険性のある状況であったことは明らかである。そして、Aが居室内のトイレに行く際にナースコールをして職員を呼ぶのを常としていたことからすると、Aが初回のナースコールをした後は、尿意等を募らせたAが、やむを得ず単独で便座に移動しようとし、その際転倒して生命や身体に危険が及ぶような重大な傷害を負う可能性があることは、職員において十分に予見することができたというべきである。したがって、被告は、Aが排せつのために、トイレ内からナースコールをした場合、その職員をして、速やかにAのもとに駆け付け、見守り、介助して、Aの転倒を防止すべき義務を負っていたというべきである。にもかかわらず、職員は、本件事故当日、Aが複数回にわたってナースコールをしているのに、その都度、Aに待つように伝えただけで、初回のナースコールから約20分後にAが転倒した状態で発見されるまでの間、Aのもとに駆け付けなかったのであるから、被告は、上記義務を怠ったものと認定しました。
二審裁判所は、本件事故は、当日の午後6時10分頃から午後6時25分頃までの間に、Aから3回又は4回のナースコールがあった後、午後6時30分頃までの間に発生した事故である。仮に1回目のナースコールが自室に戻ったことを伝える趣旨の定型的な習慣であったとしても、Aとしては同じ趣旨のナースコールを2回以上する必要はないから、2回目以降のナースコールは、職員にトイレの介助を求める趣旨のものであったと考えるのが自然である。したがって、一審被告の職員としても、少なくとも2回目以降のナースコールについては、トイレの介助を求める趣旨のものであることを認識していたといえるし、少なくともそのように認識できたといえる。また、トイレの介助を求めて複数回にわたりナースコールをしても、その度に待つように伝えられるのみであった場合、排便又は排尿を我慢できなくなったAが、自ら立ち上がって便座に移動しようとすることは、ごく自然な行動の1つといえる。しかも、Aは、職員が手助けしなくても、自分でトイレの中の手すりを持って立ち上がり、車椅子から便座に移動することまでは可能であり、そのことは職員も認識していた。したがって、仮に、本件事故直前、一審被告の職員がナースコールに「待ってくださいね」と応答したのに対し、Aから「はい」とのみ返答を受けていたとしても、そのやり取りが複数回続いた場合には、Aが自ら立ち上がって便座に移動しようとすることを職員も予見できたと認定しました。
また、一審被告は、本件事故については結果回避可能性がなかった旨を主張しました。
これに対し、二審裁判所は、本件事故については、予見可能性が認められ、かつ、複数回にわたるナースコールのうち最後のナースコール(3回目又は4回目のナースコール)の時点で職員がAの居室に駆け付けていれば結果を回避できたのであるから、それにもかかわらず、職員の人数が足りなくて駆け付けることができなかったという理由のみで、一審被告が結果回避義務を免れるとするのは相当でない。確かに、一審被告は、県内の他の施設と比べて多くの職員を配置しており、入居者定員と看護職及び介護職の合計数との割合は、介護保険法令で定められた基準の3:1を超える2.1:1である。もっとも、Aが入所していた本件施設2階には、昼間の入浴時間帯(朝食後、昼食後を含む。)は介護職員が3名ないし4名配置されているのに対し、夕食後の時間帯は2名しか配置されておらず、そのような配置の結果、Aのように転倒リスクが低いとされる入所者何人かを15分程度待たせる常況にあることは、職員も認識していたことが認められる。仮に一審被告において、職員の勤務時間帯をずらしても、法定労働時間の関係で夕食後の時間帯の配置人員を増やすことができないのであれば、利用者各人の食事の時間帯をより細かくずらすこと等を含め、よりきめ細やかな他の方策を検討すべきであり、かかる方策によって本件事故の結果を回避する可能性もあったといわざるを得ない。結果回避義務がないという一審被告の主張は採用できないと判断したものです。
ポイント
介護施設での職員等の過失が争われた事例は多く、事案に応じて判断は分かれています。
名古屋地方裁判所令和6年2月7日判決(自保ジャーナル2174号)は、被告老人介護施設に入所している80歳代男子Aが、被告施設の介護職員Yの介助を受けながらおやつのバウムクーヘンを摂取した際に誤嚥し、約11カ月後に死亡した事案につき、本件施設の職員にバウムクーヘンの提供自体を差し控えるべき注意義務や救急隊への救護要請を行うべき注意義務違反の各注意義務違反があったとは認められないとして、原告らの請求を棄却しました。
名古屋高等裁判所令和4年3月22日判決(自保ジャーナル2126号)は、要介護認定等級1を受ける68歳男子Aが、Yのデイサービスを利用して昼食中、窒息による低酸素脳症により死亡した事案でのY職員らの過失につき、Yの看護師及び介護職員らに、Aの異常発見が遅れた過失や異常発見後等の対応に過失を認めることはできないと否認し、Xらの請求を棄却しました。