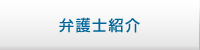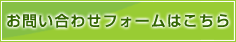肺がんを見落としたことによって、適切な治療を受けることができずに死亡
患者(60代・男性)が、癌家系であることや体重減少に不安を持ち、癌専門の医療機関に1年通院していたが異常は指摘されなかった。その1年後に胸部痛やリンパのしこりを自覚したため、別の医療機関を受診したところ、右肺がんと診断され翌年死亡したケースについて、500万円の示談が成立した事案
本件は癌を心配した患者が専門医療機関に自ら通っていたにもかかわらず、癌の見落としがあったというケースであり、死亡前の患者の悲嘆(カルテにも「癌にならないように先生を信じてずっと診察受けていたのに、どうしてこんなことに・・」との訴えが記載されていました)や遺族の嘆きには大きいものがありました。
肺癌を疑うべき症例として、日本医師会雑誌の特集が「体重減少を主訴に来院したケース」「体重減少と全身倦怠を主訴に来院したケース」を指摘しています。その他の基本的な文献でも、「非特異的な全身症状の訴えは、適切な精密検査を示唆するとともに、医師が適切な治療を選択する上での手助けになる」とされています。
本件では禁煙指数1200以上の患者に10キロ以上の急激な体重減少がありました。また腫瘍マーカーであるCEAも上昇していましたが、胸部CTなどの諸検査は実施されていませんでした。
1年後に他の医療機関で肺癌を指摘した際には、ステージⅣの末期進行がんと診断され、直ちに抗がん剤による化学療法を受けましたが死亡に至りました。
裁判では、患者の主訴をもとに精密検査を実施して直ちに適切な治療を行うべき注意義務、喀痰細胞診を実施すべき注意義務などが争点となったものです。
そして1年前に肺癌と診断したとした場合の因果関係も大きな争点になりました。本件の「非小細胞がん」は、進行度(病気)に応じて治療方針が定められるとともに生存率も決まっています。そこで原告が主張する時点において、精密検査を実施して肺癌を発見して直ちに適切な治療をしていれば、死亡の時点において生存していた高度の蓋然性があると主張したものです。
遺族本人尋問、そして主治医を含む医師2名の尋問を経て、裁判所から和解案が示されて500万円にて和解が成立しました。